12月号:Feline Focus volume1, Issue12, December 2015の概要を抜粋してご紹介致します。
原文は下記にて会員登録(無料)して頂くと入手可能です。
http://icatcare.org/nurses/membership/apply
| Topics | Anaesthetic complications and emergencies 抜粋 Running successful dental clinics Benefits of running a Cat Friendly Clinic Health problems in the newborn kitten 抜粋 Christmas hazards |
|---|---|
| State of Art | Anaesthetic complications and emergencies 麻酔に伴う合併症および救急対応 Sam McMillan著 |
| Special interest | Health problems in the newborn kitten 新生猫の健康問題 Alexandra Taylor著 |
|---|
- ○体重編
- 初産の場合、比較的小さな子猫である場合が多く平均して子猫の出生時体重は90‐110g
- 毎日体重測定実施(5g以上の体重減少があれば、原因を探ること)、10〜30g/dayの増加が一般的である。
- 体重増加がない場合、あるいは体重が少ない場合下記のような原因が考えられる
・低体温
・脱水
・呼吸器障害
・感染症 - 2〜3時間間隔で母乳を摂取(この際、母乳を吸引できていることをきちんと確認すること)
- ○新生猫の健康チェック事項
- 先天性疾患の有無:口蓋裂(サイミーズで多い)や口唇断裂、臍帯ヘルニア、四肢形成不全、肛門形成不全、尿管開口不全、多指など
- 呼吸状態の観察:呼吸頻度や様式の変化が認められたら感染症の可能性あり
- 個々の行動観察:母猫や兄弟猫の刺激に対する反応、病気の子猫の場合孤立しがいである
- 排尿、排便:下痢の有無、尿の濃縮(脱水を示唆)、排便を促すためにコットンを丸めたものなので肛門を刺激する
- 腹部:極端に細い腹部⇒十分に食べていないことを示唆
極端に膨らんだ腹部⇒便秘を示唆
※Fading kitten syndromeとは、生後数週間以内に衰弱あるいは死亡する状態を表す。
このような状態に陥る可能性のある原因は下記の通り外傷、出生異常、環境要因、低血糖、脱水、同種溶血現象、感染症
- ○体温管理
- 生後2週間の子猫や神経質であったり経験の浅い母猫によって子猫があちこちに移動させられるような場合に低体温や低血糖に陥りやすい。
- 新生児は体温維持が困難であるため、特に体温を放散するのができないためヒートパッドによる加温のしすぎにも注意が必要である。(体温の変化 出生時:約36℃、生後2週間:38℃、7週頃までには38-39.5℃)
- ○その他新生猫で気を付けたいこと
- 低血糖:新生猫の場合特にエネルギーを必要とする一方で、蓄えることができないため母猫の母乳に全て依存している。そのため、母乳を摂取できない状況に陥るとすぐに低血糖症に陥る可能性がある。
- 臍帯感染:臍帯を介した感染
- 母乳感染:子猫は消化器症状(下痢、嘔吐)を呈する。速やかに動物病院を受診
母猫も治療の対象となる場合がある - 外傷:新生児の死亡原因の10%は生後3日以内の外傷が原因とされている
- 感染症:生後2時間以内に通常初乳を摂取することで、初乳中に含まれる抗原によってさまざまな感染症に対して免疫をつける。生後2週間、さらに初乳中の免疫抗原の効果が低下し始める4〜6週目が特に注意が必要である。
これに陥らせないためにも、異常が認められたら症状が認められたら速やかに獣医師に相談すること
- ○新生児同種溶血現象(Neonatal Isoerythrolysis:NI)
メス猫の血液型がBxオス猫 A型で、子猫がA型の場合注意が必要である。
メス猫の初乳に、A型抗原が強く含まれるためA型子猫の赤血球を破壊することで、貧血、黄疸、最悪の場合死亡する。特にB型の血液型の多い猫(British shorthair, exotic Shorthair, Devon rex, Cornish rex, Sphynx)を交配に用いる際には、注意。
NIが疑われる場合には、産後24時間は母猫からはなして世話をするかA型の他の猫の母乳で育てる

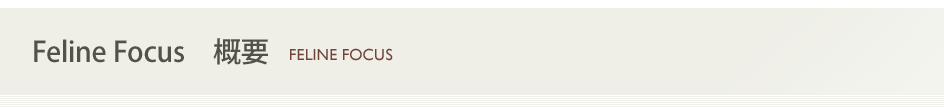
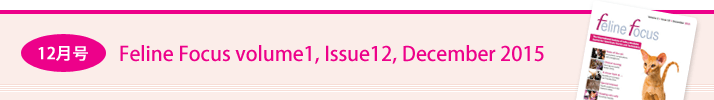


一般的に、犬と比較してサイズが小さく且つ体表面積が大きいことから低体温に陥りやすく、さらに猫はグルクロン酸抱合能を有さないため、グルクロン酸代謝に依存した薬物の過剰投与や蓄積に伴った副作用が認められやすい。
●CEPSAF(The confidential enquiry into small animal fatalities)によると79,179例の鎮静もしくは麻酔症例において、死亡リスクは平均して0.24%と報告されている。健常猫とASA Ⅲ-Ⅴの猫においてはそれぞれ0.11%と1.1%であり 同等の麻酔リスクを有する犬と比べて死亡リスクは2倍以上に相当する。
これらの合併症の60%は、麻酔維持薬を停止して3時間以内に認められることが多い。また、体重が2-6kgと比較して、2kg>の猫で麻酔による死亡率が16倍高いとの報告もある。
● 術中の適切な輸液量についてはさまざまな意見があるが、犬と比較して全血量も少ないため低血圧時や特に心疾患を有する猫に対する急激な容量負荷(ボーラス投与)には注意が必要とされる。また、未だ科学的な確証は得られていないがAAHA/AAFP fluid therapy guidelines for dogs and cats 2013によると、術中3ml/kg/hであれば肺水腫、肺機能低下、かん流圧の低下や低体温に陥らないと考えられている。
麻酔に伴う合併症には、技術的な要因に加えて猫のストレスも大きく関与している。ストレスを感じていればいるほど、保定や血管確保が困難となる。また、ストレスによってカテコールアミンが大量に放出されることで、導入中の突然死や導入薬の過剰投薬となる場合がある。そのため、軽視されがちであるが猫のストレスを極力軽減するよう入院時や扱いを工夫することが大切である。